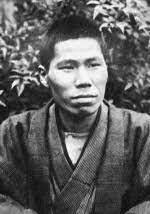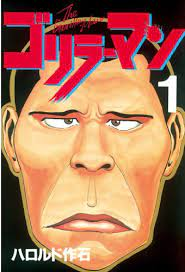現在の教科書を使うのも何週目なのか分からないのですが、今までずっと気づかずにスルーしていた部分に、今回急に疑問が沸いてしまい、個人的に考えていても結論が出ないくて、語源やら文法?やらに詳しい方に「助けていただきたい」という、割と切実なお話です。※ひょっとしたら「教科書会社に電話をかけるパート4」になるかも知れません。
さて、今回取り上げたいのは、「熟語の構成」という教材です。私立高校の入試ではデフォルトで出題される題材なので、ちゃんと教えないと「損をさせてしまう」部分です。基本は二字の熟語の、上と下の字の関係を見分ける問題なのですが、大きく5種類の構成があります。光村の教科書の分類を使うと・・・・・・
①意味が似ている漢字の組み合わせ。
拡大→拡(ひろげる)+大(おおきい) 例 思考・規則・縮小・山岳・搭乗など
②意味が対になる漢字の組み合わせ。
善悪→善(よい)+悪(わるい) 例 前後・売買・強弱・禍福・慶弔など
③主語と述語の関係。
地震→地が震える 例 国営・雷鳴・日照・人造など
④下の漢字が上の漢字の目的や対象を示す。
洗顔→顔を洗う 登山→山に登る 例 開会・造園・遷都・帰郷・就職など
⑤上の漢字が下の漢字を修飾する。
軽傷→軽い傷 激増→激しく増える 例 水路・熱心・俊足・猛犬・逆流など
というのが教科書の説明です。で、私がここの授業をやるときには、まず各自にランダムで「二字の熟語」をひとつノートに書かせておき、上の5種類の分類を説明したあとで、さっきランダムで書いた各自の熟語が、どれに当てはまるかを聞く、という流れでおこなっています。毎年、どれに分類するか迷う熟語が出て困ったり、逆にどれなのかを考えるのも面白かったりします。
極力、教科書の例は使わずに、その場で出された生徒の例をノートしてもらうことにしているので、ほぼ教科書の例は見ません。(ただし、③の例、つまり「〇が〇する」の、間に「が」が挟まるパターンは、一人もいないことが多いので、これだけは教科書の例を使うことがままあります。)
さて、今年の授業の中で「①のパターンだった人?」と発問し、いろいろな答えが出た中で、「拡大」と答えた子がいました。
それに対して私は「うーん、それは似た意味のものではなくて、『大きく拡が
(げ)る』という意味だから、④のレ点が入るパターンじゃないかな」と返答しました。すると、その子も周りの子も、なんだか微妙な顔をしているのです。
で、その段階で初めて教科書に目を落としましたら・・・・・・何ということでしょう!

①のところの例に、「拡大」がちゃんと載っているじゃあーりませんか!
 吉本新喜劇は全く好きじゃないですが、合掌。
吉本新喜劇は全く好きじゃないですが、合掌。
偶然なのか、それとも自分で考えるのが面倒で教科書を見たのかわかりませんが、そりゃ教科書で①のところに載っていれば、①のところで答えますよね。でもですよ?
そもそも意味は「大きく拡げる(拡がる)」ですよね?
「拡がる」+「大きくなる」とか 「拡げる」+「大きくする」って、無理筋じゃないですか?
さらにいえば 拡げる(拡がる)=動詞で、大(きい)=形容詞ですよね?動詞と形容詞を、「似た意味」として並べるのは、アリなんでしょうか?
(しかもご丁寧に「縮小」=「小さく縮める」も載ってます。これも縮む(める)=動詞 小さい=形容詞 ですよね?)
「広大」なら「広い」+「大きい」で、似た意味というのは分かるんです。(「狭小」も)今までずっとスルーしてきたけど、一度気づいてしまうとどうしても引っかかってしまうし、そもそも生徒に説明できません。
今年初めて気づいたのですが、どうして「拡大」は、④ではなく①なのががわかりません。どなたか助けてください。このままだとまた教科書会社に電話することになってしまいます。それはそれでネタとしておいしいけれど(←こらこら)
 コメントでご教授いただければありがたいです。
コメントでご教授いただければありがたいです。

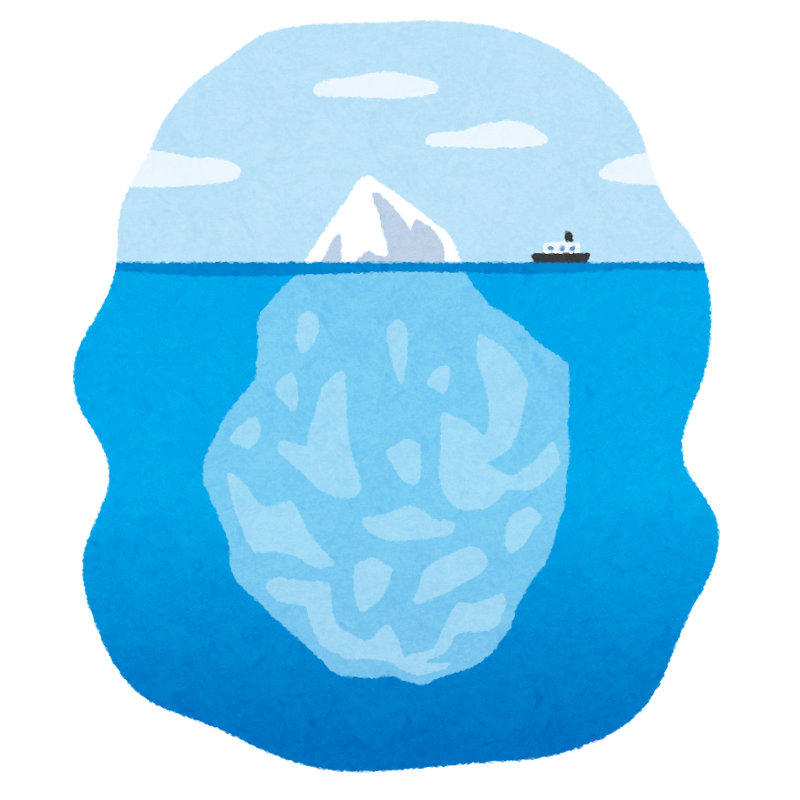 教科書の氷山は「一角」ではなく丸めでしたが。
教科書の氷山は「一角」ではなく丸めでしたが。








 ←ずっと昔からネタの宝庫だったこれ、アニメ化ですってね!驚き!
←ずっと昔からネタの宝庫だったこれ、アニメ化ですってね!驚き!

 (……何でもかんでも貼りゃぁいいってもんじゃないぞ)
(……何でもかんでも貼りゃぁいいってもんじゃないぞ)
 で、4月1日からは
で、4月1日からは



 ちょっと使い過ぎだなぁこれ。
ちょっと使い過ぎだなぁこれ。